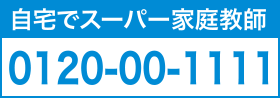KATEKYO知恵袋
気温1度上昇で何が変わる?環境を守るために私たちができること
2025年10月01日

2025年の夏も記録的な猛暑が続きました。日本全国で35℃を超える猛暑日が例年より増加し、ニュースでは連日のように熱中症の注意報が流れています。では、なぜ毎年こんなにも暑くなるのでしょうか?それには「気候変動」、つまり地球規模で起きている“夏の気温の上昇”が関係しています。このコラムでは、今年の暑さをきっかけに、「気候変動」や「温暖化」について、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
まず、よく混同されがちなのが「天気」と「気候」です。
天気は「今日の空模様」。「晴れ・雨・曇り」や「暑さ・寒さ」など、毎日の変化を指します。
一方、気候は「長い期間(年単位・十年単位)の天気のパターン」。たとえば、「日本の夏は蒸し暑い」「冬は寒い」と感じるのは気候の特徴です。
天気は「日々の天気予報」、気候は「その土地の平均的な気候傾向」と考えてください。地球の気候が変化してきた背景こそ、今、とても大切な問題なのです。
過去100年間で、地球の平均気温は約1℃(0.77℃)上昇しています。これは、1891年から2024年までの長期的な観測データに基づいた結果で、特に1990年代半ば以降は高温の年が増え、上昇傾向が加速していることがわかっています。
また、2024年の世界の年平均気温は、1991年から2020年の30年平均値と比較して+0.62℃上昇し、1891年の統計開始以降で最も高い記録となりました。
ちなみに、日本国内ではこの100年で約1.35℃も上昇しており、世界平均よりも大きな変化が見られます。都市化の影響や地域特有の気候要因も関係していると考えられています。
一見「1℃くらいなら大したことないのでは?」と思えるかもしれませんが、少しの気温変化が、私たちの暮らしや地球環境に深刻な変化を起こします。
- 耐えられない暑さが増える:35℃以上の猛暑日がぐっと増え、夏の暑さが今よりずっと厳しくなり、熱中症にかかる人も増えるでしょう。
- 大雨や洪水が増える:これまで経験したことのないような激しい雨が頻繁に降るようになり、洪水や土砂崩れの危険性が高まります。
- 食料が手に入りにくくなる:気候の変化で農作物が育ちにくくなったり、魚がとれなくなったりして、食べ物の値段が上がったり、手に入りにくくなったりするかもしれません。
- 健康への影響:熱中症や、蚊が媒介する感染症(デング熱など)が広がりやすくなることも心配です。
- 氷が溶けて海が広がる:北極や南極の氷がどんどん溶けて、海水が増え、海面が上がります。そうすると、低い土地にある国や島が海に沈んでしまうかもしれません。
- 生き物が住む場所をなくす:気温の変化についていけない植物や動物は、住む場所をなくしたり、絶滅してしまったりする可能性があります。これは、地球全体の生態系のバランスを崩すことにつながります。
- 異常な天気が増える:猛烈な暑さ、激しい雨、強い台風、そして水不足になる干ばつなど、これまでにないような極端な天気が頻繁に起こるようになります。
国際的な研究によって、たった1℃の変化がこれらの変化を加速させることが明らかになっています。
特に、もともと貧しい国々では、これらの変化に十分対応できないため、飢饉や病気、災害の被害がさらに深刻になることが懸念されます。
1. 太陽と地球の関係
太陽の活動が変わると地球に届くエネルギーが増減するほか、地球の軌道や地軸の傾きの変化も、長い周期で気候に影響を与えます。
2. 温室効果ガスの増加
地球を包む大気には二酸化炭素(CO₂)やメタン(CH₄)などの「温室効果ガス」が含まれています。これらは太陽光を通して地面を温めた赤外線を惑星の外へ出さないようにする働きがあり、地球を暖かく保っています。
しかし、人間の活動によってCO₂などが急激に増加しすぎると、大気に熱が逃げずに蓄えられすぎてしまうのです。これが「地球温暖化」の主な原因です。
3. 大気や海洋の循環の変化
地球の気候は、大気の流れ(風)や海流によって調整されています。しかし、温暖化が進むとこの循環が乱れ、たとえば「日本の北から冷たい空気が入る」「湿った空気が集まりやすくなる」など、局地的な天候の異常が増えやすくなります。
自然の中にある植物や氷などには、長年の地球環境の変化を知るヒントが隠れています。
【氷床(ひょうしょう)コア】
南極や北極にある巨大な氷を深く掘ると、古い氷が出てきます。そのなかに閉じ込められた気泡には、過去何千年もの大気成分が含まれています。
【年輪(ねんりん)】
山の木の年輪は、1年ごとの気象状態を記録しています。太い年輪は温暖で雨が多かった年、細い年輪は寒かった年、と読み取れるのです。
【珊瑚礁(さんごしょう)】
海の中でも、珊瑚は気温・塩分濃度などに敏感。同心円の模様には過去の海の状態が記録されています。
これらを調べることで、地球の気候変動は自然の力だけでなく、人間の活動からも大きな影響を受けていることがはっきりわかっています。
私たちの便利な生活は、知らず知らずのうちに地球温暖化の原因となる温室効果ガスを排出しています。ここでは、主な排出源とその影響を見ていきましょう。
車やバス、飛行機といった移動手段は、ガソリンなどの燃料を燃やすことで大量の二酸化炭素(CO₂)を排出します。私たちの移動が便利になるほど、その排出量は増え続けています。
工場で製品を作る際や、私たちの生活に必要な電気を作る発電所では、石炭や石油、天然ガスなどを燃やしてエネルギーを得ています。私たちが電気を使えば使うほど、温室効果ガスは増えていきます。
意外かもしれませんが、食料品の生産も温室効果ガスに大きく関わっています。特に、牛や豚などの家畜のげっぷにはメタンガスが含まれており、これはCO₂よりも強力な温室効果ガスです。また、農作物の栽培に使われる肥料からもガスが発生し、さらに食料を生産するための土地や水の使用も環境に大きな負荷をかけています。
森林の減少
森林は、空気中のCO₂を吸収してくれる「地球の肺」とも言える存在です。しかし、開発のために木が切り倒されたり、森林火災で燃えたりすると、CO₂の吸収量が減るだけでなく、蓄えられていたCO₂が放出されてしまいます。
世界中で人口が増えるにつれて、私たちの生活はより便利になり、その結果、必要なエネルギーや食料の量も増大しています。これは、温室効果ガスの排出量をさらに増加させる要因となっています。
地球温暖化を食い止めるために、私たち一人ひとりが日々の生活の中でできることはたくさんあります。小さな心がけが、大きな変化につながるのです。
1. エネルギーやゴミを減らす
家の中で使う電気やエアコンの設定温度に気をつけたり、お風呂の残り湯を洗濯に利用するなど節水に取り組んだりすることで、エネルギーの無駄遣いを減らすことができます。
2. 交通手段を工夫する
車やバイクの利用を減らし、できるだけ徒歩や自転車、公共交通機関を使うようにしましょう。これらはガソリンなどの燃料を消費しないため、CO₂の排出を抑えることができます。
3. 食べ物や暮らしを見直す
地産地消(地域で生産されたものをその地域で消費すること)を心がけ、近くでとれた食材を選ぶことで、食材を運ぶためのエネルギーを減らせます。また、食べ残しを減らす意識を持つことも大切です。
買い物の際は、できるだけマイバッグや容器を持参して、プラスチックごみを減らしましょう。そして、食べ物や衣類、雑貨など、本当に必要なものを必要な分だけ買うようにし、どうしても出てしまうゴミは、できるだけリサイクルに回すなどして再利用しましょう。
4. 緑を大切にする
植物はCO₂を吸収してくれる大切な存在です。自宅で花や野菜を育ててみたり、公園や地域の緑化活動に参加したりして、身近なところから緑を大切にすることで、CO₂吸収力を高める手助けができます。
一度きりの地球、みんなで築く未来
今回のコラムで、気温がたった1℃上がるだけで、地球や私たちの生活が大きく変わってしまうことが伝わったでしょうか。未来の地球と、そこに暮らすみんなが元気に過ごせる社会のために、今のうちに「あたりまえ」を見直して、家族や友達と一緒にできることから始めてみませんか?