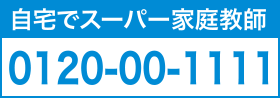新着情報
新着・更新情報などをご案内します
古代の天文ショー?
2025年10月03日
皆さま、9月8日の皆既月食はご覧になられましたか?私はスマホでバッチリ写真を撮ってしまいました。
皆既月食とは、地球の影が月を完全に覆い隠し、太陽の光が月に届かなくなり、月が赤っぽい色になる現象です。
さて、この特別な天文ショーですが、世界の歴史に古くからどう影響してきたのでしょうか?



インカ帝国では、月食は『ジャガーが月を襲っている』と考えられていました。人々は大きな音を立ててジャガーを追い払い、月を救おうとしました。一方、古代中国では、『龍が月を食べている』と信じられ、これは皇帝の権威の失墜を予兆する不吉な現象とされていました。そのため、龍を追い払うための儀式が盛んに行われました。古代メソポタミアでは、月食は王様への脅威と見なされました。災いを避けるため、月食の間だけ王様の身代わりを用意し、本物の王様は身を隠すというユニークな風習がありました。また、アメリカ先住民、特にカリフォルニアのフパ族やルイセノ族は、月食を『月が怪我をした状態』と考えていました。彼らは月を癒すために、歌などを歌う儀式を行いました。何とも優しい民族ですね。
皆既月食は知恵を持つ者に利用されることもありました。1504年、探検家のクリストファー・コロンブスは、ジャマイカでの食料取引がうまくいかなくなった際、この天文現象を巧みに利用しました。彼は暦の知識を使い、先住民に月食を予言したんです。そして予言通りに月食が起こると、驚いた先住民はコロンブスを神と崇め、食料取引は無事成功しました。
平安時代から鎌倉時代にかけての日本では、月食は『月が蝕む(むしばむ)』という言葉が示すように、不吉な現象と捉えられていました。貴族たちはその光に当たらないよう身を隠したり、お坊さんがお経を読むことで災いを避けようとしました。しかし、江戸時代に入り天文学が発展すると、月食は予測が可能な科学的現象として理解されるようになります。『不吉な予兆』から『美しく神秘的な自然現象』へと、捉え方が大きく変わっていったんですね。
今回、皆既月食を見逃してしまった方、まだ諦める必要はありません。次回、日本で見られる皆既月食は、来年の2026年3月3日です。ぜひ次回も、古代の人々が感じた神秘に思いを馳せながら、夜空を見上げてみてはいかがでしょうか。
藤枝教室 パワフル先生